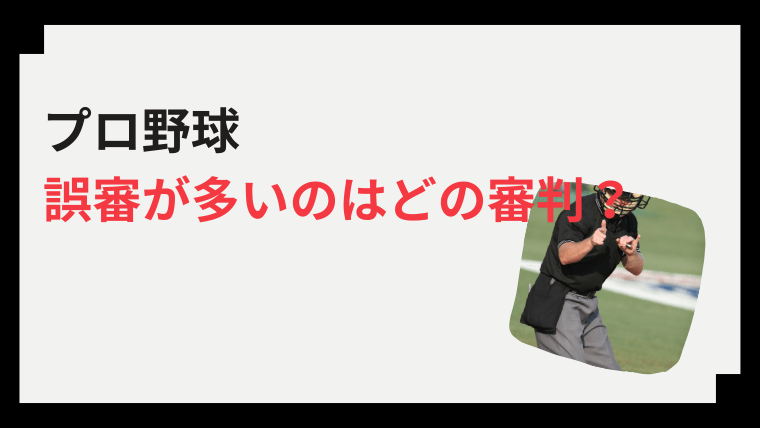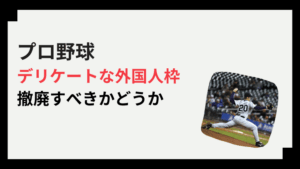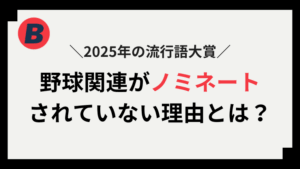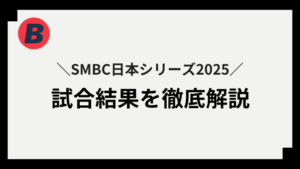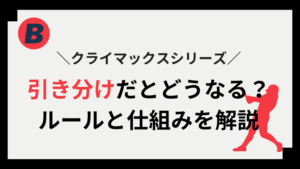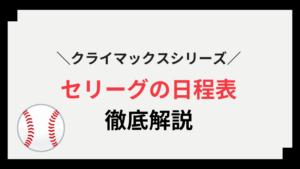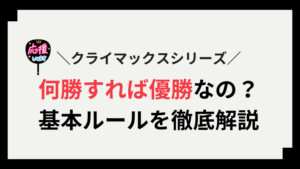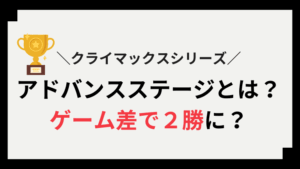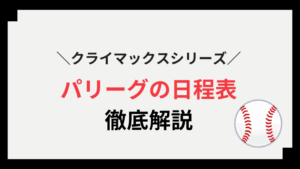プロ野球の試合を観戦していると、時折「今の判定は?」と首をかしげたくなる瞬間はありませんか。
特に勝敗を左右する場面でのジャッジには、多くのファンが注目します。近年はリクエスト制度が導入されましたが、ストライク・ボールの判定は依然として球審の判断に委ねられており、これが議論の的になることも少なくありません。
中には、プロ野球審判の誤審ランキングや誤審率について気になる方もいるでしょう。また、物議を醸す判定をした誤審審判のその後や、プロ野球界としての誤審への処分がどうなっているのか、疑問に思うかもしれません。
この記事では、そうしたプロ野球における審判の判定問題に焦点を当て、誤審が多いと指摘されることがある審判の具体的な事例から、判定を機械化するAI審判の導入に向けた現状まで、詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点が明らかになります。
- 誤審で注目されやすい審判の具体的な名前や事例
- 審判が誤審を指摘された場合の処分やその後のキャリア
- ストライク・ボール判定におけるAI審判の導入状況
- プロ野球の審判が抱える課題と今後の展望
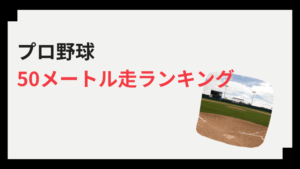
プロ野球で誤審が多い審判がいる現状

- 誤審が注目される眞鍋勝己審判員
- 物議を醸した小林和公審判員の判定
- ネットで有名な山路哲生審判員の事例
- プロ野球審判の誤審ランキングはある?
- 誤審とは違う?個性的な審判員たち
誤審が注目される眞鍋勝己審判員

プロ野球界で長く審判を務める眞鍋勝己審判員は、豊富な経験を持つ一方で、そのジャッジがファンの間で議論を呼ぶことがあります。
関西統括ディレクターという要職にも就いていますが、時折、判定が注目を集める場面が見られます。
例えば、過去のソフトバンク対オリックス戦での出来事が挙げられます。
一塁でのクロスプレーに対し、塁審はアウトと判定しました。もちろん、このプレーはリクエストの対象となり、ビデオ判定が行われました。しかし、映像ではセーフにも見えるタイミングでしたが、判定は覆らずアウトのままとなったのです。
この時の球審を眞鍋審判員が務めていたこともあり、リクエストを経ても判定が変わらなかったことに対して、多くのファンから疑問の声が上がりました。審判団の責任者クラスであるだけに、その一つ一つのジャッジがより厳しく見られる傾向にあるのかもしれません。
物議を醸した小林和公審判員の判定
元プロ野球選手(ヤクルト)という経歴を持つ小林和公審判員も、長いキャリアを誇る審判の一人です。しかし、時にその判定が物議を醸すことがあります。
特に記憶に新しいのは、阪神対中日戦で見られたストライク判定です。試合終盤の9回表という緊迫した場面で、明らかにボールゾーンと思われる投球をストライクと判定したことが大きな話題となりました。一度だけでなく、同じイニングで二度も同様の判定があったため、選手やファンも納得がいかない様子でした。
野球の試合、特に接戦の終盤におけるストライク・ボールの判定一つは、試合の流れを大きく変えてしまいます。そのため、このような判定が続くと、審判への信頼性が揺らぎかねないという指摘も出ています。
ネットで有名な山路哲生審判員の事例
審判の判定の中でも、特にファンの記憶に強く残っているのが山路哲生審判員の事例です。山路審判員は、短期間に複数の誤審と受け取られかねない判定を下したことで、一躍その名が知られることになりました。
2017年4月に行われた広島対DeNA戦では、一塁塁審を務めていた山路審判員が、1試合で2度も際どいタイミングのプレーをアウトと判定。
リプレイ映像では明らかにセーフに見えたため、広島の監督が猛抗議しましたが、判定は覆らず、監督は退場処分を受けました。
さらに、この判定について試合後に問われた山路審判員が「ジャッジした通りです」とコメントしたことも、ファンの感情を逆撫でする結果となったのです。
さらに、その約2週間後の中日対DeNA戦では、本塁でのクロスプレイをセーフと判定。これもリプレイではアウトに見えるタイミングであり、結果的にこのプレーが決勝点となり中日は敗れました。
抗議した選手は暴力行為とみなされ退場処分となるなど、後味の悪い試合として記憶されています。これらの出来事から、「山路=誤審」というイメージが定着してしまいました。
| 年月日 | 対戦カード | 球場 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2017年4月19日 | 広島 vs DeNA | マツダスタジアム | 6回と7回の一塁走塁判定がアウトに。リプレイではセーフに見えた。 |
| 2017年5月2日 | 中日 vs DeNA | ナゴヤドーム | 9回の本塁クロスプレイをセーフと判定。これが決勝点となった。 |
プロ野球審判の誤審ランキングはある?

「誤審が多い審判は誰か」という関心から、プロ野球審判の誤審ランキングのようなものが存在するか気になる方もいるかもしれません。
しかし、日本野球機構(NPB)が公式に審判員の誤審率やランキングを発表することはありません。
審判の判定は絶対的なものとして尊重されるべきであり、機構が公式に優劣をつけるようなデータを公表することは、審判の権威を損なうことになりかねないからです。
ただ、非公式ながら、野球ファンや一部のメディアが独自にデータを集計し、特定の審判の判定傾向などを分析することはあります。
SNSやブログなどで「〇〇審判はストライクゾーンが広い」「××審判は際どい判定が多い」といった形で話題に上り、それが事実上のランキングのように認識されているのが実情です。
誤審とは違う?個性的な審判員たち
審判員が注目されるのは、必ずしも誤審だけが理由ではありません。中には、そのユニークなジェスチャーやコールでファンから親しまれている個性的な審判員もいます。
その代表格が、敷田直人審判員です。彼の見逃し三振のコールは、腕を力強く振り下ろすポーズが「卍(まんじ)」に見えることから、「卍の敷田」として野球ファンに広く知られています。このポーズは、彼自身が試行錯誤の末にたどり着いたスタイルであり、試合を盛り上げる一つの名物ともなっています。
また、白井一行審判員もその甲高い独特のコールで有名です。「ストライク」とは聞こえず、「アアアアイイイッッッ!」という奇声のようにも聞こえるコールは、広い球場でもよく響き渡り、一度聞いたら忘れられないインパクトがあります。
このように、審判員それぞれの個性に注目してみるのも、プロ野球の楽しみ方の一つと言えるかもしれません。
プロ野球で誤審が多い審判問題への対策
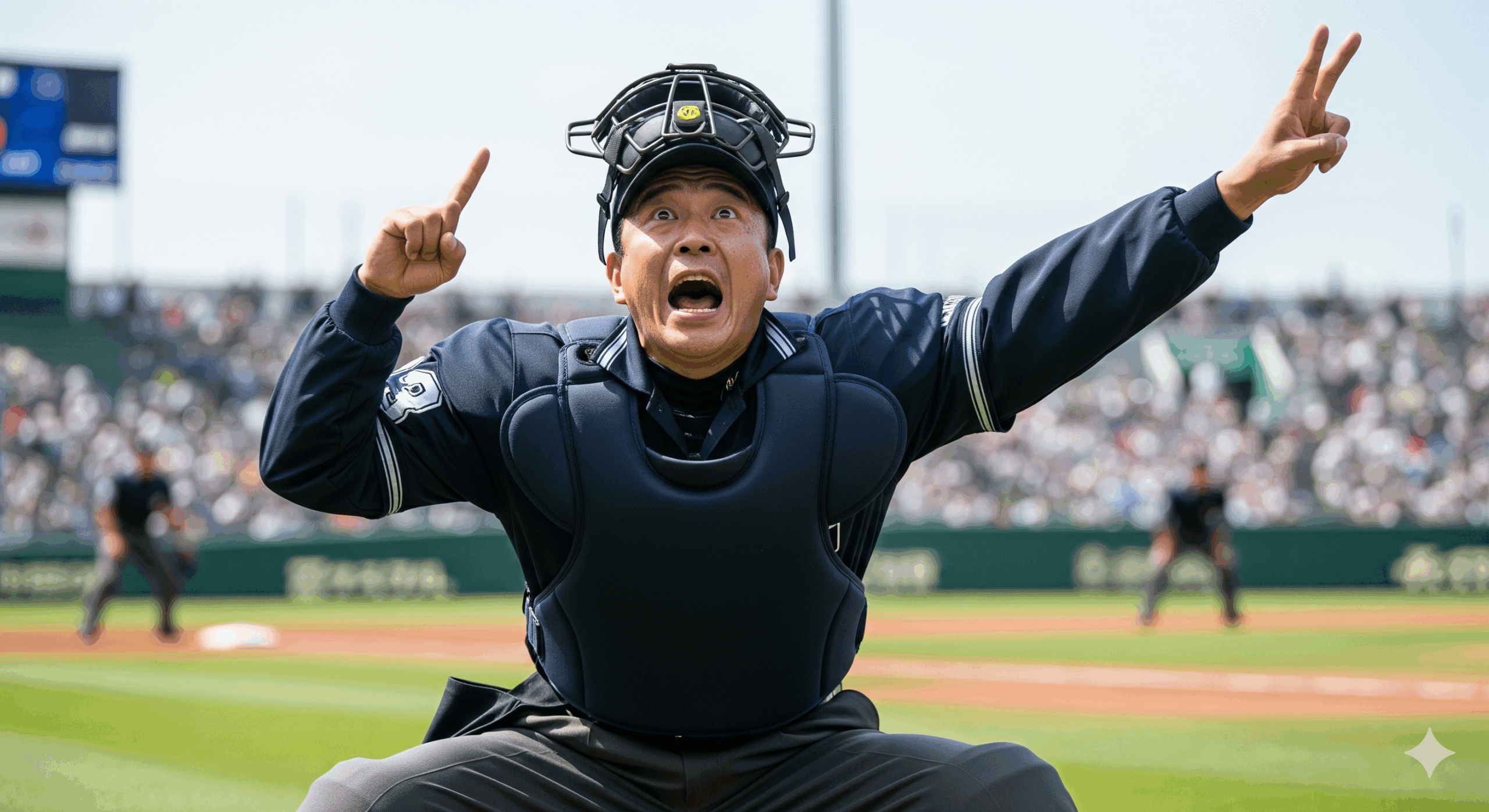
対策のポイント
- プロ野球審判の誤審率はどれくらいか
- プロ野球における誤審の処分はあるのか
- 誤審審判のその後はどうなるのか
- ストライク判定のAI化はいつから?
- AI審判導入のメリットと今後の課題
- プロ野球の誤審が多い審判問題の総括
プロ野球審判の誤審率はどれくらいか
プロ野球審判の正確な誤審率について、公式なデータは公表されていません。前述の通り、NPBが審判のパフォーマンスを数値化して公開することは、審判制度の根幹を揺るがす可能性があるためです。
したがって、「〇〇審判の誤審率は△%」といった具体的な数字を知ることはできません。
誤審率の算出が難しい理由の一つに、「何をもって誤審とするか」という定義の曖昧さも挙げられます。リクエスト制度によって覆った判定は明確な誤審と言えますが、リクエスト対象外のストライク・ボール判定については、見る人によって意見が分かれることがほとんどです。
テレビ中継のCG映像と実際の判定が異なっていたとしても、それが即座に誤審とは断定できないのが現状です。人間の目で一瞬のプレーを判断している以上、100%完璧なジャッジは極めて難しいと考えられます。
プロ野球における誤審の処分はあるのか
ファンとしては、明らかな誤審をした審判には何らかの処分が下されるべきだと考えるかもしれません。しかし、実際には1回の誤審で審判が即座に罰金や出場停止といった公の処分を受けるケースはほとんどありません。
山路審判員の事例でも、抗議した監督や選手が退場や制裁金の処分を受けた一方で、審判員の判定そのものに対する処分は不問に処されました。これは、審判の判定を最終的なものとし、その権威を守るというリーグの姿勢の表れです。
ただし、処分が全くないわけではありません。度重なる判定ミスや著しくパフォーマンスが低いと判断された審判は、担当する試合のランクを下げられたり、日本シリーズのような大舞台のメンバーから外されたりといった、内部的な評価に影響すると言われています。あくまで公にならない形での評価や指導が行われているのが実情です。
誤審審判のその後はどうなるのか
一度や二度の誤審、あるいは物議を醸す判定によって、審判員が即座に職を失うことはありません。審判員はNPBとの契約の下で働いており、その身分は一定程度保障されています。
誤審を指摘された審判員も、基本的には翌日以降も通常通り審判としての業務を続けます。もちろん、内部での反省会や映像を見返しての研修などを通じて、ジャッジの精度向上に努めることが求められます。
大きな注目を集めた判定を下した直後は、心理的なプレッシャーも大きいと考えられますが、それを乗り越えてグラウンドに立ち続けなければなりません。
長い目で見れば、判定の安定性や正確性は昇進や担当試合の割り振りにも関わってくると考えられます。審判もまた、厳しい競争の中で技術を磨いているプロフェッショナルなのです。
ストライク判定のAI化はいつから?
ストライク・ボールの判定を巡る議論が絶えない中、解決策として期待されているのがAI審判、すなわち「ABS(Automated Ball-Strike System)」の導入です。
NPBではこの問題に対し、2019年から検討委員会を設置して議論を重ねています。そして、2020年からはファーム(2軍)の公式戦でABSのテスト導入を開始し、実用化に向けたデータ収集と検証を続けている段階です。大学野球や社会人野球の一部でも試験的に導入されており、技術的な精度は年々向上しています。
しかし、1軍の公式戦へいつから本格導入されるかについては、まだ明確な時期は示されていません。メジャーリーグでも同様にマイナーリーグでのテストが進んでいますが、トップリーグへの導入には慎重な姿勢が見られます。
したがって、日本のプロ野球でもAI審判が導入されるのは、早くても2025年以降になると考えられており、まだしばらくは人間によるジャッジが続く見込みです。
AI審判導入のメリットと今後の課題
AI審判の導入には、多くのメリットが期待されています。最大の利点は、もちろん判定の公平性と一貫性です。
投球のコースをミリ単位で正確に追尾し、設定されたストライクゾーンを通過したかどうかを機械的に判断するため、人間のような判断のブレがなくなります。
これにより、判定を巡る不毛な争いが減り、試合がスムーズに進行することが期待できるでしょう。
一方で、導入には課題も少なくありません。
技術的な課題
まず、システムの精度と信頼性の確保が不可欠です。カメラやセンサーの誤作動、悪天候時の影響など、あらゆる状況下で100%正確に稼働するという保証が求められます。
人間的要素の喪失
また、「野球の人間的な要素が失われる」という意見も根強くあります。捕手のフレーミング技術(ボールに見える球をストライクに見せる技術)が無意味になったり、審判と選手間の駆け引きがなくなったりすることを懸念する声です。
コストの問題
さらに、全試合・全球場に高精度なシステムを導入するための莫大なコストも課題となります。これらの課題をクリアし、選手やファンが納得する形で導入できるかが、今後の鍵となりそうです。
プロ野球の誤審が多い審判問題の総括
- プロ野球では審判の判定が試合結果を左右することがある
- 眞鍋勝己審判員や小林和公審判員は経験豊富だが判定が議論を呼ぶことがある
- 山路哲生審判員は過去に短期間で複数の誤審を指摘され有名になった
- NPBが公式に審判の誤審ランキングや誤審率を発表することはない
- ファンやメディアが非公式に特定の審判の判定傾向を分析することはある
- 敷田直人審判員の「卍」ポーズなど個性で人気の審判もいる
- 白井一行審判員は甲高い独特のコールで知られる
- 1回の誤審で審判が公に処分されることは稀である
- 審判のパフォーマンスは内部評価や担当試合に影響するとされる
- 誤審を指摘されても審判はキャリアを継続し技術向上に努める
- ストライク判定のAI化(ABS)が解決策として期待されている
- NPBでは2020年からファームの試合でAI審判をテスト導入中
- 1軍への本格導入時期は未定で、早くても2025年以降と見られる
- AI審判のメリットは公平性と一貫性の向上である
- 課題として技術的信頼性、人間的要素の喪失、コストなどが挙げられる
-
落合博満氏の妻・信子さんの現在は?2026年最新状況
-
【2026年】プロ野球の外国人枠は5人?基本的な仕組みを徹底解説
-
巨人イケメンランキング2026年最新版!TOP10を徹底解説
-
流行語に野球用語がないのはなぜ?ノミネートなしの理由を解説
-
【速報】日本シリーズ2025の結果は?現在の勝敗と今後の日程
-
【徹底解説】クライマックスシリーズは引き分けになるとどうなる?
-
【2025年最新版】セリーグクライマックスシリーズ日程速報!
-
クライマックスシリーズは何勝で勝ち?ルールと仕組みを完全網羅!
-
【2025年最新】クライマックスシリーズ日ハムチケット完全ガイド
-
【2025年最新】クライマックスシリーズ阪神チケット完全ガイド