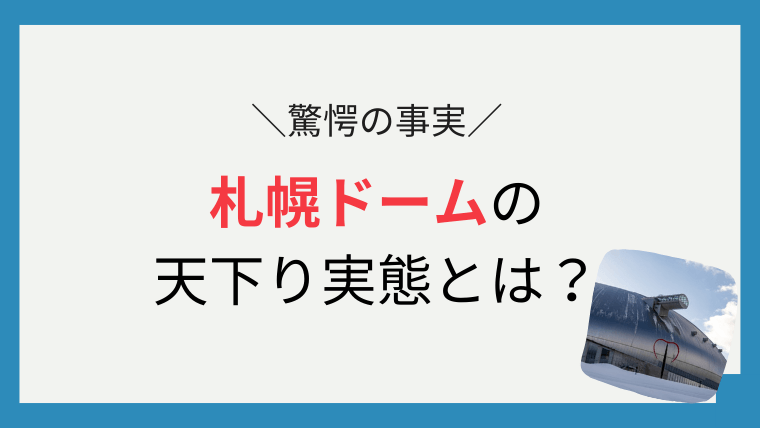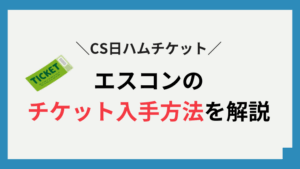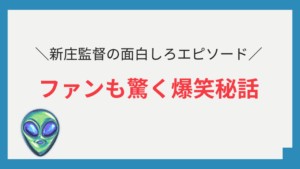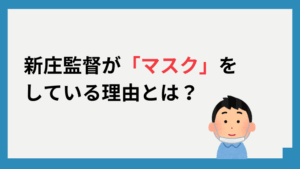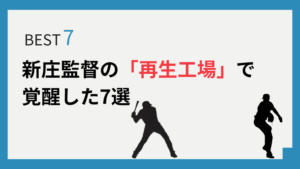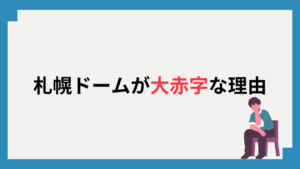北海道日本ハムファイターズの新球場移転により、深刻な経営危機に直面している札幌ドーム。
2025年現在、年間赤字6.5億円という厳しい状況の背景には、札幌市からの天下り役員による杜撰な経営実態があることが明らかになっています。
株式会社札幌ドームの主要役員は、ほぼ全員が札幌市の元幹部職員で構成されており、実質的に札幌市の天下り先として機能していることが問題視されています。
 速報ネコ
速報ネコFightersは本当にエスコンフィールドに移籍してよかったと思います!
札幌ドームの天下り実態について解説
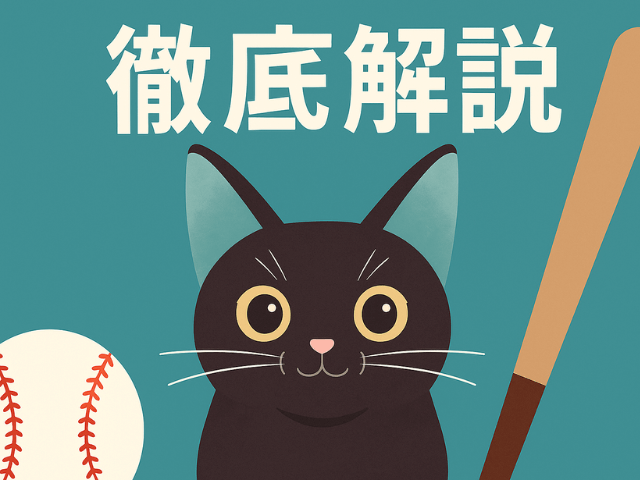
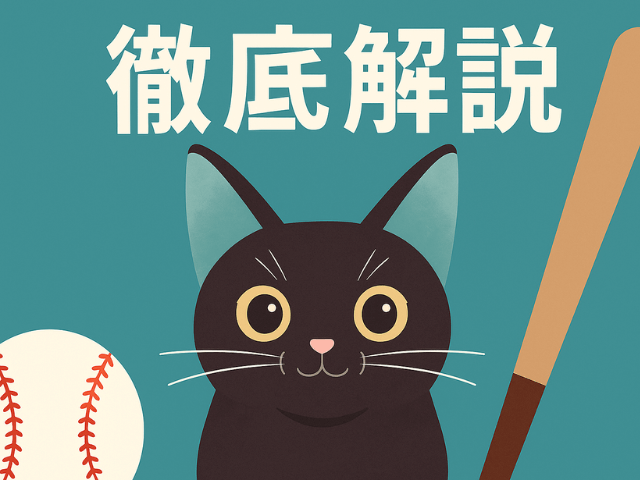
札幌ドームを運営する株式会社札幌ドームは、表向きは第三セクターの民間企業ですが、実態は札幌市の天下り先として機能しています。
現在の経営陣を見ると、社長を除く主要役職のほぼ全てが札幌市の元幹部職員で占められており、民間企業としての経営感覚が著しく欠如している状況が浮き彫りになっています。
札幌ドーム天下り役員の構成
- 社長:山川広行(北海道銀行出身・矢面に立たされた存在)
- 副社長:石川敏也(元札幌市副市長)
- 常務取締役:藤部安典(元札幌市総務局職員部共済担当部長)
- その他役職も札幌市OBが多数占有
- 社員給与は公務員準拠でベースアップも実施
札幌市副市長から副社長に就任した石川敏也氏の経歴
札幌ドームの副社長を務める石川敏也氏は、札幌市副市長を経験した典型的な天下り役員です。
石川敏也氏は長年にわたって札幌市の行政職員として勤務し、副市長という要職まで上り詰めた後、株式会社札幌ドームの副社長ポストに就任しました。
石川敏也氏の経歴を見ると、行政畑一筋で民間企業での経営経験は皆無に等しく、収益性を重視する民間経営の感覚が身についていないことが問題となっています。
札幌市副市長時代には法規や条例に基づいた「決められたこと」をする業務が中心で、経済状況の変化に応じて臨機応変に対応する能力や、収益を追求する発想に乏しいことが指摘されています。
このような背景を持つ石川敏也氏が札幌ドームの副社長として経営に関わることで、日本ハムファイターズが札幌ドームを去った理由や、ドーム運営における問題点を根本的に理解することができず、適切な対策を講じることができない状況が続いています。
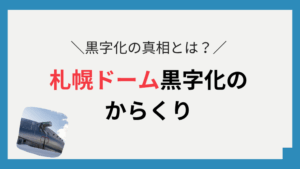
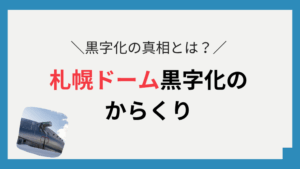
札幌市職員部長から常務取締役になった藤部安典氏
札幌ドームの常務取締役を務める藤部安典氏は、札幌市総務局職員部共済担当部長という行政職から直接転身した典型的な天下り人事の事例です。
藤部安典氏の前職である職員部共済担当部長は、主に市職員の福利厚生や共済制度の運営を担当する部署であり、民間企業の経営や収益管理とは全く異なる業務領域でした。
藤部安典氏が常務取締役として札幌ドームの経営に参画していることで、民間企業として必要な経営判断や収益改善策の立案・実行が困難になっていると考えられます。
特に、日本ハムファイターズとの関係悪化や使用料交渉などの重要な局面において、民間企業としての柔軟性や顧客重視の姿勢を示すことができず、結果として主要テナントを失う結果を招いたとも言えるでしょう。
また、藤部安典氏のような行政出身者が経営陣に就くことで、札幌ドームの組織文化自体が公務員的な体質になり、変化への対応力や危機意識の欠如を生んでいる可能性も指摘されています。


北海道銀行出身の山川広行社長
札幌ドームの社長を務める山川広行氏は、北海道銀行取締役副頭取から2017年に第三セクターの社長に就任しました。
山川広行氏は唯一の民間企業出身者として社長ポストに就いていますが、実質的には「矢面に立たされている」存在と見られています。
山川広行氏が社長に就任したタイミングは、日本ハムファイターズの新球場移転が決定した後であり、札幌ドームの経営危機が明らかになってからの就任でした。このため、山川広行氏は札幌ドームの善後策を担う使命を負わされており、厳しい状況での経営を余儀なくされています。
しかし、山川広行氏が民間出身であっても、副社長や常務取締役といった実質的な経営陣が全て札幌市の天下り役員で固められているため、根本的な経営改革を実行することは困難な状況にあります。
また、株式会社札幌ドームが実質的に札幌市の外郭団体として機能しているため、山川広行氏の民間的な経営手法を導入することにも限界があると考えられます。
札幌ドーム歴代社長は無能なのか?経営手腕を検証
札幌ドームの経営陣について、その経営能力や手腕に疑問を呈する声が多く聞かれています。特に日本ハムファイターズの退去決定以降、年間赤字6.5億円という深刻な経営状況に陥っていることから、歴代社長や現経営陣の責任を問う声が高まっています。
札幌ドーム経営陣の問題点
- 民間経営の経験や感覚の欠如
- 収益性よりも既得権益の維持を優先
- 顧客満足度向上への意識の低さ
- 危機管理能力の不足
- 札幌市の意向に左右される経営判断
歴代社長の経歴と在任期間中の業績
札幌ドームの歴代社長を見ると、その多くが行政出身者や地元金融機関出身者で占められており、エンターテイメント事業や施設運営の専門知識を持った人材は皆無に等しい状況でした。
特に施設開業以来の経営陣は、札幌市の意向を強く反映した人事が続いており、真の意味での民間企業としての経営が行われてこなかったことが明らかです。
歴代社長の在任期間中の業績を見ると、日本ハムファイターズが好調だった時期でも根本的な収益構造の改善は図られず、ファイターズ頼みの経営体質から脱却することができませんでした。
また、施設の老朽化対策や新たな収益源の開拓についても十分な対策が講じられず、結果として現在の経営危機を招く原因を作ったと言えるでしょう。
現在の山川広行社長についても、民間出身でありながら札幌市の天下り役員に囲まれた環境で真の経営改革を実行することは困難であり、根本的な問題解決には至っていないのが現状です。
札幌市幹部の「官尊民卑」意識が経営に与える影響
札幌ドームの経営問題の根本には、札幌市幹部職員による根深い「官尊民卑」の意識があります。データベースによると、札幌市の幹部職員は地元の北海道大学などの有名大学出身者が多く、民間企業や民間人を見下す傾向があるとされています。
この「官尊民卑」意識が最も顕著に表れたのが、日本ハムファイターズの新球場移転問題での札幌市側の対応でした。札幌市側は「せっかく札幌市が野球やらせてやったのに、わがままばかり言いやがって」という認識を持っており、日本ハムが札幌ドームを出て行った理由を全く理解していませんでした。
このような意識を持った札幌市幹部の天下り役員が札幌ドームの経営陣を構成していることで、顧客である日本ハムファイターズや一般利用者のニーズを軽視し、自分たちの都合を優先する経営姿勢が形成されてしまいました。
結果として、主要テナントである日本ハムファイターズとの関係が悪化し、最終的な退去決定につながったと考えられます。
民間経営センスの欠如が招いた赤字6.5億円の現実
札幌ドームの天下り役員たちに共通する最大の問題は、民間経営センスの決定的な欠如です。行政職員は法規や条例に基づいて「決められたこと」をするのは得意ですが、経済状況の変化に即して臨機応変に動くことができず、収益を求めるような仕事についての発想が根本的に欠けています。
この民間経営センスの欠如が最も顕著に表れたのが、現在の年間赤字6.5億円という深刻な経営状況です。日本ハムファイターズという主要な収益源を失った後も、根本的な経営改革や新たな収益源の開拓に取り組むことができず、単に札幌市に対して経費や管理費の付け替えを要求するような対応に終始しています。
また、社員の給与体系が公務員に準拠しており、経営状況に関係なくベースアップが実施されるなど、民間企業としては考えられない人事制度が維持されています。
このような体制では、経営危機に対する危機感や改革への意識が生まれるはずもなく、結果として問題の先送りと赤字の拡大を招いているのが現状です。
札幌ドームが日本ハムファイターズに嫌がらせをした真相
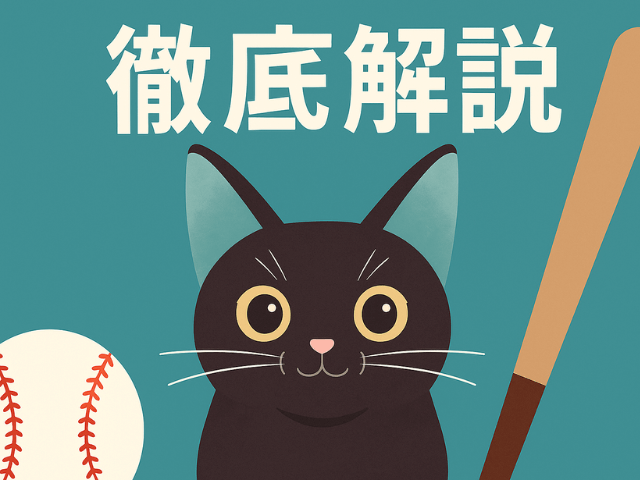
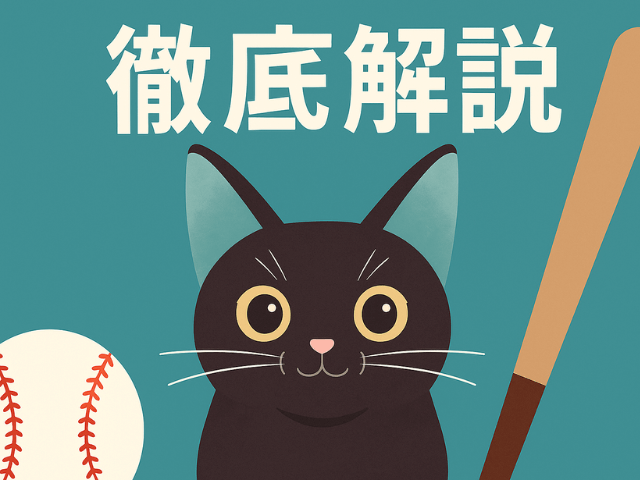
札幌ドームと北海道日本ハムファイターズの関係悪化については、単なる経営上の意見の相違を超えて、札幌ドーム側による意図的な嫌がらせ行為があったのではないかという疑問の声が上がっています。特に札幌市幹部の「官尊民卑」意識に基づく上から目線の対応が、ファイターズ側の不信感を決定的なものにしたと考えられています。
札幌ドーム側の問題行動
- 「プロ野球やらせてやった」という恩着せがましい発言
- 使用料や運営面での一方的で高圧的な対応
- ファイターズの要望や意見を軽視する姿勢
- 新球場移転決定後の逆恨み的な言い訳や批判
- 民間企業としての顧客サービス意識の完全な欠如
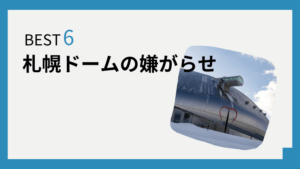
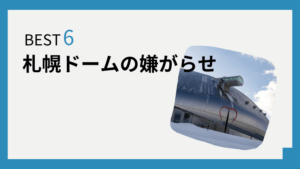
「プロ野球やらせてやった」発言に見る上から目線
札幌ドーム側の問題意識を端的に表しているのが、関係者による「せっかく札幌市が野球やらせてやったのに、わがままばかり言いやがって」という発言です。この発言からは、札幌市および札幌ドーム経営陣が、日本ハムファイターズを「やらせてやっている」という上から目線で見ていたことが明らかです。
本来、プロ野球球団と球場運営会社は対等なビジネスパートナーの関係であり、互いに利益を追求し合う関係であるべきです。しかし、札幌ドーム側は日本ハムファイターズを「札幌市が恩恵を与えてやっている相手」として認識しており、この根本的な認識の誤りが関係悪化の最大の原因となりました。
このような発言の背景には、札幌市幹部職員による根深い「官尊民卑」の意識があり、民間企業である日本ハムファイターズを下に見る姿勢が常態化していたことがうかがえます。こうした意識を持った天下り役員が札幌ドームの経営を担っていたことで、顧客重視の姿勢が完全に欠如し、結果として主要テナントを失う結果を招いたのです。
使用料や運営面での日本ハム側の不満とは
日本ハムファイターズが札幌ドームに対して抱いていた不満は、使用料の高さだけでなく、運営面での様々な制約や非協力的な姿勢にありました。プロ野球球団として最高のパフォーマンスを発揮し、ファンサービスを向上させるために必要な要望に対して、札幌ドーム側が非協力的な対応を続けていたことが大きな問題となっていました。
具体的な不満の内容としては、球場施設の改善要望に対する消極的な対応、イベント開催時の制約の多さ、ファンサービス向上のための提案に対する理解不足などが挙げられます。
また、使用料についても、他球場と比較して割高であるにも関わらず、サービス内容が見合っていないという不満も強く持っていました。
さらに問題だったのは、こうした日本ハム側の要望や不満に対して、札幌ドーム側が真摯に向き合おうとする姿勢を全く見せなかったことです。民間企業であれば顧客の要望に最大限応えようとするのが当然ですが、札幌ドーム側は「嫌なら出て行けばいい」という高圧的な姿勢を崩すことがありませんでした。
ファイターズ退去決定後の札幌ドーム側の言い訳と対応
日本ハムファイターズの新球場移転が正式決定された後の札幌ドーム側の対応は、さらに問題の深刻さを浮き彫りにしました。本来であれば、主要テナントを失った原因を真摯に反省し、今後の経営改善に活かすべきところを、札幌ドーム側は一貫して責任転嫁と言い訳に終始しました。
特に問題だったのは「プロ野球やらせてくれないのでね」という発言で、これは日本ハム側が一方的に出て行ったかのような印象を与える明らかな責任逃れの発言です。実際には、札幌ドーム側の長年にわたる非協力的な姿勢と高圧的な対応が、ファイターズの移転決定を招いたにも関わらず、その責任を全く認めようとしませんでした。
また、新球場移転決定後も、札幌ドーム側は根本的な経営改革に着手することなく、札幌市に対して経費の付け替えや支援の要請を行うなど、依存体質から脱却しようとする姿勢を全く見せていません。
このような対応からは、問題の本質を理解し、改善しようという意志が全く感じられず、今後の経営改善への期待も持てない状況となっています。
札幌ドーム経営破綻の戦犯は誰?責任の所在を追及
札幌ドームが現在の深刻な経営危機に陥った責任の所在を明確にすることは、今後の対策を検討する上で不可欠です。年間赤字6.5億円という状況を招いた戦犯として、札幌市の天下り体制そのものと、それを維持し続けた札幌市の政策判断に最大の責任があると考えられます。
札幌ドーム経営破綻の主要因
- 札幌市による天下り先確保を優先した人事
- 第三セクターの構造的な問題と責任の曖昧さ
- 民間経営センスの完全な欠如
- 顧客軽視の経営姿勢
- 危機管理能力の不足
第三セクター運営の構造的問題点
札幌ドームを運営する株式会社札幌ドームは、表面上は民間会社でありながら、実質的には札幌市の外郭団体として機能している典型的な第三セクターです。
この第三セクターという運営形態そのものが、今回の経営破綻の根本的な原因となっています。
第三セクターの最大の問題は、責任の所在が曖昧になることです。経営が順調な時期には「民間企業として自主的な経営を行っている」と主張し、経営が悪化すると「公共性の高い事業のため行政の支援が必要」と使い分けることが可能になってしまいます。
札幌ドームもまさにこのパターンを踏襲しており、都合の良い時だけ民間企業を名乗り、困った時には札幌市への依存を深めるという構造になっています。
また、第三セクターでは株主である自治体の意向が強く反映されるため、本来の企業経営よりも政治的な判断が優先されがちです。札幌ドームの場合、札幌市の天下り先確保という政治的な目的が最優先され、収益性や経営効率は二の次とされてきました。この結果、民間企業としての競争力や危機対応能力が全く育たず、現在の経営危機を招いたのです。
公務員準拠の給与体系とベースアップの実態
札幌ドームの経営問題を象徴的に表しているのが、社員の給与体系が公務員に準拠していることです。民間企業であれば、経営状況に応じて給与水準を調整するのが当然ですが、札幌ドームでは経営が悪化している中でも、公務員と同様にベースアップが実施されています。
この給与体系の問題は、単に人件費が高いということだけでなく、組織全体の意識に深刻な影響を与えています。経営状況に関係なく給与が保証されることで、社員の危機意識や改革意欲が削がれ、「何もしなくても給与はもらえる」という公務員的な体質が組織全体に蔓延してしまいました。
また、このような給与体系を維持することで、札幌ドームは実質的に札幌市の一部門として機能することになり、民間企業としての自立性や競争力を完全に失ってしまいました。
年間赤字6.5億円という状況でありながら、根本的な人事制度の見直しが行われていないことは、経営陣の危機意識の欠如を如実に物語っています。
札幌市の天下り先確保が最優先された経営体制
札幌ドームの経営破綻の最大の戦犯は、天下り先の確保を最優先に考えた札幌市の政策判断にあります。札幌市は株式会社札幌ドームを実質的な外郭団体として位置づけ、市の幹部職員の退職後のポストを確保するための組織として活用してきました。
この天下り優先の人事政策により、札幌ドームの経営陣は民間企業としての経営能力よりも、札幌市との関係性や政治的な調整能力を重視された人材で占められることになりました。
その結果、顧客満足度の向上や収益性の追求といった、本来の企業経営に必要な能力が軽視され、現在の経営危機を招く原因となりました。
また、天下り役員の存在により、札幌ドームの経営判断は常に札幌市の意向に左右されることになり、迅速で柔軟な経営判断が困難になりました。
日本ハムファイターズとの関係悪化についても、民間企業であれば顧客の要望に最大限応えようとするところを、札幌市の面子や既得権益を優先した結果、最終的な退去決定を招いてしまったのです。
大阪ドーム破綻事例に学ぶ札幌ドームの未来予想
札幌ドームの現状を理解する上で、非常に参考になるのが大阪ドーム(現京セラドーム大阪)の破綻と復活の事例です。大阪ドームも札幌ドームと同様に第三セクターによる運営で経営破綻に陥りましたが、オリックスによる買収後は見事に経営を立て直し、現在は黒字経営を続けています。
- 第三セクター運営では必然的に経営破綻する構造
- 民間企業による買収が唯一の解決策
- 球団と球場の一体経営の重要性
- 施設改修と収益源多様化の必要性
- 自治体からの独立が成功の鍵
大阪ドームが第三セクターで破綻した経緯
大阪ドームは1997年に開業した際、総工事費696億円という巨額の投資で建設されましたが、開業当初から深刻な経営問題を抱えていました。
当初の経営計画では年間来場者数600万人、稼働日数300日という目標を掲げていましたが、実際には来場者数400万人、稼働日数も目標の6割程度にとどまりました。
大阪ドームの経営悪化の主な原因は、建設時の計画の甘さと、第三セクターによる非効率な運営体制にありました。
特に問題だったのは、稼働天井から発生する人工地震による周辺住民からの苦情で、大物アーティストのコンサート会場として敬遠される結果となり、野球以外の収益源を確保することができませんでした。
さらに、大阪市の第三セクターが運営していたため、民間企業のような迅速で効率的な経営改善策を実施することができず、毎年20億円程度の赤字を重ね続けることになりました。
この状況は札幌ドームの現状と非常に類似しており、第三セクターによる運営の構造的な問題を如実に示しています。
オリックスによる買収後の黒字転換成功事例
大阪ドームの転機となったのは、2006年にオリックスが施設を90億円で買収したことでした。オリックスによる買収後、大阪ドームは球団と球場の一体経営が可能となり、積極的な施設改修と収益源の多様化に取り組むことができました。
オリックスは買収後、まず施設の全面的な改修に着手しました。グッズ販売店の拡張、外野スタンド下のレストラン開業、売場面積の拡大など、飲食物販の収益向上に重点的に取り組みました。
その結果、買収から10年が経った頃には、飲食物販の収益が2倍強に増加するという成果を上げました。
また、周辺の再開発も積極的に進め、イオンモールの誘致や病院、スーパービバホームの開業など、野球やコンサートに興味がない人でも足を運べるような複合施設として発展させました。
これにより、ドームを中心とした地域全体の活性化が進み、安定した収益基盤を構築することに成功しています。
札幌ドームも民間売却しか生き残る道はないのか
大阪ドームの成功事例を参考にすると、札幌ドームが現在の経営危機から脱却するためには、民間企業への売却以外に現実的な解決策は存在しないと考えられます。
第三セクターとしての現在の運営体制を維持したまま経営改善を図ることは、構造的に不可能だからです。
札幌ドームの場合、大阪ドームと比較してさらに厳しい状況にあります。大阪ドームにはオリックス・バファローズという球団があったため球団と球場の一体経営が可能でしたが、札幌ドームは主要テナントである日本ハムファイターズを失っており、収益源の確保がより困難な状況にあります。
ただし、札幌ドームも立地条件や施設規模などの基本的なポテンシャルは決して低くありません。適切な民間企業が買収し、効率的な経営を行えば、大阪ドームと同様に黒字転換を図ることは十分可能と考えられます。重要なのは、札幌市が既得権益や面子にこだわることなく、早期の民間売却を決断することです。
札幌ドーム天下り問題の解決策と今後の展望


札幌ドームの天下り問題を根本的に解決し、経営を立て直すためには、現在の第三セクターによる運営体制を完全に廃止し、民間企業への売却を実行する以外に道はありません。大阪ドームの成功事例が示すように、民間企業による効率的な経営により黒字転換は十分可能ですが、そのためには札幌市が既得権益を手放す政治的決断が不可欠です。
札幌ドーム問題の解決に必要な対策
- 会社更生法適用前の早期民間売却
- 天下り体制の完全廃止
- 外資系(特に中国系)売却の回避
- 資産価値があるうちの売却実行
- 札幌市の政治的決断と責任の明確化
現在の年間赤字6.5億円という状況を放置すれば、札幌ドームの資産価値はさらに毀損し、将来的な売却価格も大幅に下落する可能性があります。評判の悪化とドームの老朽化を考慮すると、今後はさらに赤字幅が拡大することは避けられず、早急な対策が求められています。